
【SFプロトタイピング前編】こんな未来がくるかもしれない小説 「クリエイター・クリエイター・クリエイター」

「サキさん、宇宙美術館のアイデアコンテストに応募してみませんか?」
ジジ先生にそう声をかけられたのは、今から20年前、2040年の6月のことでした。私は小学4年生にあがってすぐで、毎日遊ぶことしかしておらず、科学や芸術のことを理解していたとは言い難いのですが、なんだかとてもワクワクしたことを覚えています。
たぶん先生は、ふだん私がVRゲームや粘土工作、そして昆虫飼育などを一人でずっとやっているという話を聞いて、なにか秘められた私の才能を見抜いたのかもしれません。ジジ先生はSFプロトタイピング担当教員という役職で、一人一人の生徒の能力を見ながら将来に繋がる創造的なプロジェクトを提案することを仕事にしていたのです。
この当時、すでにAIの発展はかなりのものになっていました。型にはまった授業であればAI教員が個々の進捗を見ながら適切に進行してくれるようになったので、人間の教員はこうして対人コミュニケーションで能力を伸ばすことに特化した役職を担い始めたという過渡期でした。
「詳しくお話しますと、とある会社が、これから20年かけて宇宙空間に美術館を作ろうって考えているとのことで、そのコンセプトを募集しているそうなんです」
「すっごく興味ある! でも先生、そんな難しいこと私にできるの?」
「難しい部分は他の人やAIに任せればいいんですよ。サキさんならきっとできます。興味さえあるなら、僕は全面的にサポートしますよ」
ジジ先生はいつものように丁寧な口調で、ニコニコしながらそう言いました。このときはまさか、これが自分の人生を決定づける瞬間だとは思いもしませんでしたが、「ついに運命が訪れた」と自分が物語の主人公になったような不思議な気分になったことをよく覚えています。
こうして、私の青春の日々が幕を開けました。
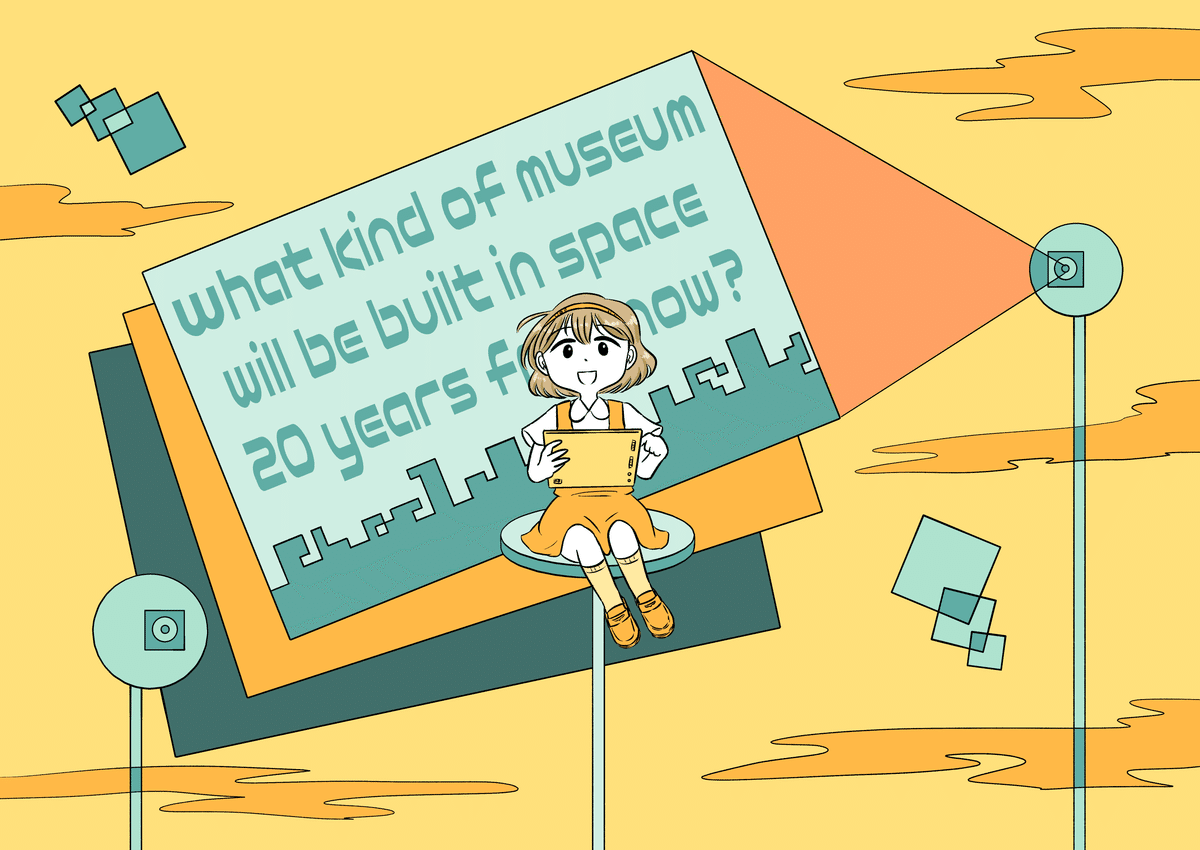
ジジ先生はまず、「AIプラットフォーム」というものを教えてくれました。そのオンラインプラットフォームでは、建築、宇宙科学、美術など、様々な専門的用途に沿って機能するAIソフトウェアが発表されています。あの時代は、あらゆるジャンルの専門家が、こぞって自分でクリエイトしたオリジナルAIを発表していた全盛期でした。
ここを見て、まずは自分たちに何ができそうか考えようというのが、ジジ先生の指示でした。当時の私には何がなんだか分からない難しい事柄もありましたが、そこは私に付いてくれている教育用AIが丁寧に意味を教えてくれたり、なによりジジ先生が親切に質問に答えてくれたりしたので、私は楽しくプラットフォームに触れることができました。
学校の端末からインターネットにアクセスし、知らない世界に入ってみるというのは、もちろんそれまでの私も 行っていたのですが、このような「仕事」的な専門性が絡んだ世界を見るのは初めてでした。
「ジジ先生、この建築家さんのAIが作ってるお城、どれもキレイだよ」
「サキさん、この宇宙科学の研究者さんは、かなり面白そうな研究をしていますね」
「このAIが描く絵画、めちゃめちゃインパクトある!」
先生と私はそんな話をしながら、AIが出力した作品や研究をたくさん見て、自分たちの宇宙美術館のイメージを膨らませていきました。
プロジェクトを始めて数日経つと、ジジ先生は「そろそろ気になったAIを使ってみようか」と言い出しました。
「さすがにそんな難しいことはできない」と戸惑う私に、ジジ先生はいつものニコニコ顔で「簡単ですよ」と返します。
当時、AIクリエイターが誰にでも自分の作ったAIを使えるように公開するというのは、まだそれほど一般的ではありませんでした。そもそもAIを作るハードルが、ほんの少しだけ高かったからです。とはいえ、一部の先進的なAIクリエイターは、様々な条件付きのもと、AIを 無料で公開 し ていて、先生は私にそういったカテゴリのAIを紹介してくれていました。
「気になったAIはどんどん呼び出して、話をしてみればいいんですよ」
先生がニコニコと勧めてくるので、私はとりあえず目についた建築系のAIにコンタクトを取って、話してみることにしました。
「こんにちは。私、サキって言います。宇宙に美術館を作るアイデアのコンテストに応募してみたいと考えていて、あなたを使わせて頂けたらと思っています。あなたなら、どう宇宙美術館を作りますか?」
「宇宙空間では重力の方向にとらわれずに物が移動できるため、例えば定期的に位置が組み変わるような四次元建築ができるのではないでしょうか?」
「よ、よじげん……!」
「時間変化も含めて設計する建築を四次元建築と私達は呼んでいます」
「なるほど……」
人のクリエイトしたAIに話しかけるのはなんだか恥ずかしく、どう話しかけていいかと戸惑った記憶もありますが、たしか、そのような会話をしたはずです。AIプラットフォームの過去ログを辿れば、録画も残っているかもしれません。いまでは個人のAIと大企業のAIの違いなどを深く考える人は少ないと思いますが、当時はAIといえば大企業の作るものという固定観念があり、まだまだ個人AI勢は珍しかったのです。
とにかく初めての会話は、拍子抜けするほど順調に進みました。
ジジ先生と私はそれから、宇宙科学者の作ったAIや、画家の作ったAI、彫刻家の作ったAIなど、様々な分野のAIと話しました。

そこから気に入ったAIだけを集めて、みんなで会話をしてもらうということもしました。
「宇宙に持っていきやすい素材や、宇宙でも壊れにくい構造で、美術館を作る必要があります」
「かつてデュシャンは便器を横倒しにした『泉』という作品によってアートを問い直しました。そういった重力方向を意識させる過去のアートを参考に展示を考えてみます」
「AIさんたち……ありがとう……!」
こうして様々なAIが意見を出してくれたおかげで、宇宙美術館のコンセプトはものすごい勢いで形になっていきました。
たまに、AIの制作者の人間の方と話すこともありました。AIをこう改善してほしいという要望を出したときに、制作者の方から直接話を聞きたいと言ってきてくれるパターンもあったのです。実はこのプロジェクトを通じて知り合った人のなかには、その後も友人関係を保ち、今でも仕事でお世話になっている方もいます。素晴らしい人生経験でした。
コンセプト設計が進むと、 ジジ先生は ニコニコしてばかりで、ほとんどプロジェクトに意見せず、 当時の私はジジ先生に「先生はやる気がないの!?」と突っかかってばかりでした。今考えると、先生は私の自主性を尊重してくれていたのだと思います。
私の親は子供の教育を育児AIに任せるタイプで、私はふだんから親にかまってもらえていませんでしたから、そもそもジジ先生が横にいてくれるだけで嬉しかったのですが、でもだからこそジジ先生の反応が欲しくて、ついつい無駄に絡んでいたのです。
さて、私が寝ている間にもAIは議論を交わし、朝目を覚ました私に、何パターンものコンセプトアートや図面が届いているという日々が続きました。私はそのなかから「これがいい」「いややっぱりあっちのほうが良かったかも」などと、ほとんど直感的に候補を絞り込んでゆきました。
なにしろ私は小学生です。なにが科学技術的に新しいか、なにがアートの文脈の上で価値を生むかなどを判断する基準をほとんど持ち合わせていません。そんな私にAIはだいぶ振り回されているようで、「解決案はありません」という回答が返ってくることもままありましたが、たいていAIは私の想像をはるかに超えた、素晴らしい解決案を出してきてくれました。
ただ、ことはそう簡単にはいきません。応募締め切り間近のある日、私は突然自信を失ったのです。

きっかけは、ほかの応募 者の情報を知ったことでした。海外の有名なクリエイター兼研究者という方が、私と同じAIプラットフォームを利用し、同じように宇宙美術館のコンセプトを作って大きな話題になっていることが、AIプラットフォームのニュースで流れてきたのです。
その瞬間、「私のオリジナリティってなんだろう」ということが、唐突に分からなくなりました。もちろんAIプラットフォームを使っている人は当時から大勢 いたわけで、それは驚くことでもないと今は当然のように理解していますが、「井の中の蛙」の小学生だった当時の私にとって、それはほとんどアイデンティティ喪失の瞬間でした。
さらにその海外の応募者の人は、AIの出してくるアイデアの細部まで理解し、まるで自我の一部であるかのようにAIを使いこなし、それらを統合した新しいAIを自らクリエイトしていました。それにひきかえ私は……「AIを使いこなしている」という感覚がまったくありませんでした。
自分はジジ先生とAIに従っているだけで、ジジ先生やAIのクリエイティビティは超えられていないのではないか、そういう気持ちで悩んでしまったのです。
もちろんジジ先生は、苦しむ私に優しく声をかけてくれました。
「人の考えやAIの考えを自分の考えと思い込まず、『これは人の考え』『これはAIの考え』『これは自分の考え』と切り分けているのは、サキさんの一番良いところです。人のAIを借りているだけで、自分の能力が高いと勘違いしている人も多いですから」
しかしジジ先生の温かい言葉が、締め切り直前で焦りに焦っていた私の心に届くことはありませんでした。ジジ先生の意見は、目の前のことしか見えていなかった当時の私には少し哲学的すぎたのです。結局私は、たくさんのAIから受け取った提案をどんどん却下して、ほとんど自棄になってAIに無理難題を押し付けまくりました。
ジジ先生からは、私の趣味である昆虫飼育をしているつもりでAIと接してみたらどうかともアドバイスも貰ったのですが、意固地になっていた私は「それはジジ先生のクリエイティビティであって私のクリエイティビティではない」とはねのけて、無視してしまいました。
そうしているうちに、私はどんどん自分のやりたいことが分からなくなり、とりあえずそれまで熱中していたVRゲームや粘土工作をそのままAIにやらせるようなイメージで、およそ普通の美術館や人工衛星などとは異なる、いびつな構造の不可能物体を提案したりもしました。
締め切り日でもその姿勢は変わらず、最後までAIが解決案を出せない課題を一部に残したままコンセプト案を提出するという、惨憺たる有様でした。
それでも、ジジ先生はニコニコと私を見守っていました。泣きながらコンセプト案を提出する私に「よくできました」と言ったジジ先生の意図を、当時の私はまったく理解できませんでした。
その後一ヶ月、審査結果の開示日まで、私はジジ先生と口も聞かなかったほど、私はジジ先生に反発していました。
そして、いよいよ「運命の日」が来ます。
さすがにこの日ばかりは、ジジ先生と私は同じ教室に集まり、インターネットでの結果発表を待ち構えました。優勝は最初から有り得ないと思っていましたが、コンテストには様々な部門がありますし、ジジ先生が審査結果は見たほうがいいとしつこく言ってくるので、なかば仕方なく見に来たのです。
結果は、本当に予想外のものでした。
「課題創造部門」グランプリ受賞。
私とジジ先生のコンセプト案が一つの部門のトップを取った……、私は呆然とすると同時に「なぜ受賞したのか」が本当に不思議でした。でも、受賞理由をプレゼンターが説明しているのを聞いて、なるほどと思いました。
「今の世界では、たいていの課題は発見されて すぐ、 AIが 解決して しまいます。しかしこのコンセプト案では、AIでも解決できない課題をたくさん創造していました。このように高度に複雑化した分野に対し、過去にとらわれない姿勢で自由に発想するというのは、本当に難しいことです。実際に20年後にこのコンセプトが実現できるかは分かりませんが、そのチャレンジングな精神をたたえ、『課題創造部門』のグランプリを授与します」
この言葉で、私の消えかけていた自信は一気に戻るどころか、しばらくは不遜なくらいに自信過剰になりました。
ジジ先生は私に言いました。
「どんな人のどんなAIをどんなふうに組み合わせて、どこに適用するか、そしてそこに理不尽で無理な注文を出せるのは、じゅうぶんに人間に残されたクリエイティビティなんですよね」
思えば、あのころから、AI自体も「作品」であり、それを組み合わせるのも「作品づくり」であるといったような認識が一般に広まっていったような気がするのですが、それ以前はAIというのは単なる「道具」といったような扱いがほとんどでした。
だからこそ先生は、これからの未来で仕事をしていかなくてはならない私に、どうAIと付き合うべきかを教えてくれたのだと思います。ジジ先生はそれからいつも、ニコニコしながらこんなことを言うようになりました。
「これからの時代は『クリエイター・クリエイター・クリエイター』的な存在、クリエイターを作るクリエイターを作るクリエイターが活躍する時代が来ますよ。つまりAIクリエイターの時代です。サキさんはその一つ一つのクリエイトの違いをしっかりと認識して良い仕事ができる人物になれるのではないでしょうか」
哲学的すぎて正直よく分からない言葉ですし、ジジ先生なりの冗談なのかもしれませんが、20年経ってこうして今、私が実際に宇宙美術館の開発に携わるようになったのは、このジジ先生のエールに感化され、宇宙美術館の「クリエイター・クリエイター・クリエイター」になりたいと強く思ったからなのでした。

以上、長くなりましたが、これで私のスピーチを終わります。
実は私はこれから、ジジ先生と久しぶりに会う予定です。記念すべき当宇宙美術館の施工開始日は、せっかくなので先生と見届けたいなと思いまして。ほとんどの進行は「私のクリエイトしたAI」のクリエイトしたAIに任せることができるので、私は先生とのんびり話してきます。
本日は、一開発者でしかない私にこうしてスポットライトを当ててくださり、本当にありがとうございました。
それでは皆さま、引き続き「施工オープニングセレモニー」をごゆっくりお楽しみ下さい。
【SFプロトタイピング後編】こんな未来がくるかもしれない漫画「変わり、変わる、変化」に続く
(作:宮本道人、絵:ハミ山クリニカ)
本作はAI inside 監修のもと、SFプロトタイピングワークショップを経て作成されました。

